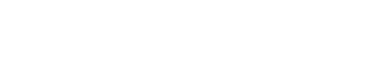日本酒を使っていつものご飯をさらにおいしく
新型コロナの影響もあり、普段よりおうち時間が伸びている今日この頃。
以前よりも、自宅で料理をする機会が増えている方も多いと思います。
実は日本酒は加えるだけで、いつものご飯がさらに、とってもおいしくなることはご存じでしょうか?
そこで今回は、意外と知られていない日本酒の料理酒としての効果と、調理の際の使い方を簡単に紹介したいと思います。

① はじめに =日本酒と料理酒の違い=
② 日本酒の料理酒として効果
③ 料理酒としての使い方
④ 終わりに
① はじめに =日本酒と料理酒の違い=
まず、今回のテーマである日本酒を料理酒として紹介をする前に、一般的なペットボトルに入った料理酒と日本酒の違いについて説明します。
どちらも料理で使うお酒のため料理酒という点では同じですが、成分とそれに伴う課税率に違いがあります。
成分については、一般的な料理酒には「塩分」が添加されており、実際に味見をしてみると塩味と甘味が強く舌に残るような味わいになっています。
こうした料理酒は「加塩料理酒」と呼ばれ酒税の対象外となることで、金額を抑えて販売することが出来るように施策されています。
2つの違いが分かったうえで注意しておきたいのは、料理のレシピを見てつくる時に料理酒と書いてある場合、「加塩料理酒」の塩味や甘味を考慮しての味付けになっている事があるため、日本酒だけでは味が物足らなくなる場合があります。
日本酒に変更して作る際は、味見を何度かおこない、後から味を加えていくようにしましょう。
② 日本酒の料理酒として効果
次に日本酒を料理に使った際の主な効果について紹介します。
皆さんもどこで聞いたことがあるかもしれませんが、大きく4つの効果が期待できます。

①素材の臭みを取る
②旨味・コクを出す
③素材への味のしみ込みをよくする
④素材をやわらかくする
①素材の臭みを取る
日本酒が料理の臭みをとるのは、お酒に含まれるアルコールとクエン酸の2つの成分によるものです。
アルコールは熱を加えることによって気化し、その際に生肉や魚の臭みを一緒に蒸発するとされています。
次にクエン酸は、生肉や魚の油に含まれる臭みを抑制させる効果があります。
この効果を十分に発揮させるためにも、日本酒は「さしすせそ」の砂糖よりも前に入れるのが良いとされています。
②旨味・コクを出す
旨味とコクを出すのは、日本酒に含まれるアミノ酸・コハク酸・糖分によるものです。
お米を原料に作られる日本酒のこれらの成分が、加熱することによって香りや風味を料理に加えてくれます。
また一説によると、精米歩合の高い日本酒よりも低いお酒の方が、お米の複雑な成分が残りやすく、料理での旨みやコクを出すのに向いている言われております。
③素材への味のしみ込みをよくする
意外と知られていないのが、日本酒が食材への味のしみ込みをよくする効果があるということです。これはアルコールの働きによるもので、お酒のアルコールが食材にしみ込む際に、他の調味料や旨味を一緒に具材にしみ込みやすくさせているためです。
ここで覚えておきたいのは、一般的な料理酒に含まれている塩分が、味のしみ込みを邪魔する作用があるということです。そのため、塩分の含まない日本酒を使用することが大切です。
④素材をやわらかくする
素材をやわらかくするのは、アルコールに食材の保水性を高める効果 があるのと合わせて、お酒に含まれる糖分が タンパク質と水分を結びつける効果によりものです。
ここでも 一般的な料理酒に含まれている塩分 が、水分を素材から出してしまう作用があるため、日本酒の方がおすすめです。
③ 料理酒としての使い方
実際に料理酒として日本酒を使う際には、次の簡単なルールを守るだけ、いつもの料理が数段おいしくなります。

①量はケチらずに大胆に
飲むことを目的で購入した日本酒ならなおさらですが、どうしてももったいない精神が働いてしまい、使う量を少なくしてしまいがちです。
しかしここは心を鬼にして料理がおいしくなるためなら、家族の皆が喜んでくれるならと考えて、大胆に使うようにしましょう。
②煮物は最初に、炒め物は仕上げに
量を意識した次は日本酒を加えるタイミングについてです。
先に紹介したように料理酒にはアルコール分が含まれるため、素材の臭みを取る効果があります。調味料の基本「さしすせそ」は順番に加えていくのが良いとされますが、日本酒は「さけ」として、「さとう」の前に入れるのが良いとされます。特に魚などの煮物をする際は、醤油やみりんと合わせた調味液を作り具材を加えたうえで火にかけることで、より臭みを取ることができます。
また、お肉や野菜などで炒め物をする際は、料理に旨味やコクをプラスすることをイメージして、すべての具材を加えた後で、フライパン全体に日本酒を振りかけて、蓋などで少し蒸し焼きにするのがおすすめです。
その場合は具材からの水分が出てくる場合があるので、日本酒を加えた後に味見をして、調味料で味を調えるといった順番を意識して頂くと失敗が少なくなると思います。
④ 終わりに
簡単ではありますが、日本酒の料理での使い方を紹介してきました。
今回記事を投稿するにあたり、料理の専門家ではないため調べながらの作業になりましたが、「なるほど」「そういうことか」と思うことがたくさんありました。
私自身も秀月の上撰や佳撰を料理酒として使うのですが、特に魚の煮付けた時は、お!!!っと思うくらいの出来栄えになります。
ぜひ飲むだけではない、お酒(秀月)の楽しみ方を探してみていただければと思います。